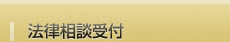第五十回渋谷法律相談センターコラム「遺留分を知っていますか?」
遺言をする人は、自分の財産を誰にどれだけ残すかを、自由に決めることができます。
たとえば、法律上の相続人が複数いるのに、全財産を一人の相続人だけに相続させるという遺言や、相続人ではない赤の他人に全財産を遺贈する(遺言で贈与する)という遺言も有効です。
でも、遺産がもらえないと生活に困る相続人もいますし、遺産相続への期待が裏切られたと感じる相続人もいるでしょう。そこで、民法は、相続人に最低限の相続財産の取得を認めるために、「遺留分」という制度を用意しています。
「遺留分」は、配偶者や子供が相続人の場合、遺産全体の半分に対して、自分の法定相続分の割合に従って主張できます。
たとえば、相続人が妻と長男・長女の3人で、遺産が自宅土地建物(3000万円相当)と預金(1000万円)の場合に、「全財産を長男に相続させる」という遺言が残されたとき、妻と長女が長男に「遺留分」を主張するケースを考えてみましょう。
自宅と預金の合計が4000万円で、その半分は2000万円。
妻は夫の遺産について2分の1、長女は4分の1の法定相続分がありますので、妻は2000万円の2分の1にあたる1000万円、長女は4分の1にあたる500万円の金銭支払いを、長男に求めることができます。この権利を、「遺留分侵害額請求権」といいます。
この権利は、民法の改正で、2019年7月1日以降に発生した相続について認められるようになりました。実は、それ以前は、「遺留分減殺(げんさい)請求権」といって、それぞれの遺産について遺留分の割合での現物返還を求められるにすぎず、それだと不動産は共有状態になってしまうため、相続をめぐる紛争が長引く原因にもなっていました。
金銭請求権に変わったことは一歩前進ですが、そもそも、遺留分を侵害しないような遺言を残すことで、相続後の紛争を防げるのであれば一番ですよね。
当法律相談センターでは、本年2月から3月にかけて、遺言・相続に関する無料相談会を開催します。遺言の内容について迷っている方は、是非この機会にお気軽にご相談ください。